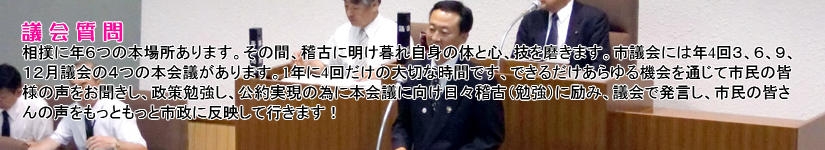平成17年12月議会議事録 |
志賀光法失礼いたします。新政会の志賀光法でございます。本日最後の登壇でございます。30分ほどおつき合いのほどをよろしくお願いいたします。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 |
藤田市長志賀議員の御質問にお答えをいたします。 |
前田教育長 |
志賀光法ありがとうございました。それでは、自席から、要望なり質問をさせていただきたいと思います。 |
前田教育長お答えします。 |
志賀光法ありがとうございました。一部ふえる学校もあるようですが、ほとんどの学校で今後増加は見込めない、ほとんどの学校が減少する。特に、小野についてはびっくりしておるところでございます。それで、教育長に大変答えにくい質問をさせていただきますことをまずお許しをいただいて、質問をさせていただきたいと思います。 |
前田教育長特認校就学制度の一つの目的に、子供の学習活動の幅をより広げるという面がございます。それから、学校教育法施行規則の第17条ただし書きのところの、地域の実態その他というところは、実は、通学区域あるいはその地域にどのぐらい家なんかが密集しているか、そういうことも含めて、管理上、設備編成上、指導上等からも一つの目安としていると思っております。そうしましたことから、特認校に今の学校教育法施行規則第17条にある学級数等の規模を当てはめるということは、非常に難しいと考えております。 |
志賀光法ありがとうございました。北部5校の保護者、特にこの特認校を受けるにあたっていろんな思いがありました。北部5校の保護者にとっては、小学校に上がる前から、実は少人数教育、少人数学級の弊害というのはいろいろ感じておりました。例えば、少人数のために競争意欲が醸成されにくいとか、児童生徒間の評価が固定化されやすいとか、学校行事やクラブ活動が活性化されにくいなどの弊害、デメリットは常に感じておりました。ですから、この特認校を受けるにあたっては、それが少しでも緩和されるといいますか、先ほど教育長が言われたように、活動の場、学習の場が広がることを期待しておりました。しかしながら、この受けることにあたっては、先ほど私が聞きにくいことを質問しましたけど、このことを受けることによって廃校、統廃合の対象とならないことが担保できたらなと思ったものですから、こういう質問をさせていただきました。非常に失礼な質問をさせていただいたことをお許しいただきたいんですが、私たち保護者の本音として真摯に受けとめていただきたいと思っております。本当に申しわけございませんでした。 |
田中副議長あと3分でございます |
志賀光法わかりました。特認校制度周知の方法として、市広報掲載、説明会の開催等答弁されましたが、その辺の説明会等の時期、場所について、また啓発広報についてはチラシ、ポスター、パンフレットも私は必要だと思いますし、その辺の予算措置も必要と思いますが、その辺のお考えをお伺いいたします |
前田教育長 市広報への掲載、保護者への文書送付等については来年1月に、それから説明会の開催につきましては来年の適切な時期に、特認校の学校説明会とあわせて実施したいと考えております。これらの実施に際して、チラシあるいはパンフレット等も作成したいと思います。 |
志賀光法ありがとうございました。最後に、聞きたいことたくさんあったんですけど、最後に要望でまとめたいと思います。 |
田中副議長時間がまいりましたから、まとめてください。 |
志賀光法テレビなどの報道で、皆さん最近御存じと思いますが、相次ぐ女児の殺害事件も起こり、また全国各地で児童生徒の列へ車が突っ込むなど、相次ぐ事故も起こっております。子を持つ親としては、通学について大変不安が募るものばかりでございます。どうか、通学フリー定期、これを小学生にも拡大していただいて、2,000円で対応していただければ、子を持つ親としては大変な安全・安心が担保できるんではないかと思います。強く要望いたしまして、早口で申しわけございません、質問を終わります。ありがとうございました。 |